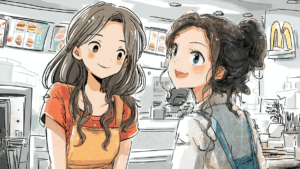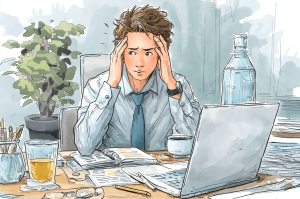もやもやした気持ち、抱えていませんか?
「またあの人、今日も休みか……」そんなふうに思ったこと、ありませんか?
体調不良で頻繁に休む人がいると、どうしても周りの負担が増え、つい迷惑だと感じてしまうものですよね。でも、だからといって強く言うこともできず、モヤモヤした気持ちを抱えたまま働き続けるのは、誰にとってもつらい状況です。
この記事では、そういった悩みを抱えるあなたに向けて、「体調不良でよく休む人に対して、職場全体でどう対応すべきか」をじっくり考えていきましょう。
職場での体験談|イライラと罪悪感の間で揺れた日々
ある事務職の女性(30代)は、同じ部署に所属するメンバーが頻繁に体調不良で欠勤するようになり、次第に負担が自分に偏ってきたといいます。
「最初は『体調が悪いなら仕方ないよね』って思っていたんです。でも、週に何度も欠勤されると、当然こちらの仕事が増える。自分の業務だけでも大変なのに、なんで私ばかり……と、心の中で何度も愚痴ってました。
そんな気持ちを抱えながらも、欠勤者に対して強く言えない状況にストレスを感じ、次第に体調を崩すようになったそうです。
「今思えば、あのとききちんと職場全体で体制を見直すべきだったんですよね。『誰かが欠けても回る仕組み』があれば、私も相手を責めずに済んだと思います」
「その後、上司に状況を相談し、業務の分担を見直すチームミーティングが開かれました。そこでタスク管理ツールを導入したり、補助担当者をあらかじめ決めるようにしたことで、私の負担はかなり軽減されたんです。
相変わらず同僚は体調を崩しがちですが、いまは『困ったときはお互いさま』と思えるようになりました。体制さえ整えば、イライラや迷惑感情も減っていくものなんだと実感しました」
FAQ|周囲のモヤモヤに答えるよくある Q&A
以下に、記事内容に合ったFAQ(よくある質問とその回答)を4つご提案します。読者の疑問や不安を事前に想定し、解消することを目的としています。
よくある質問(FAQ)
Q1:体調不良で休みがちな人に迷惑を感じるのは悪いことですか?
A:いいえ、その感情自体は自然なものです。
誰かが頻繁に休むことで、自分の業務負担が増えれば、迷惑と感じるのは当然の感情です。大切なのは、その感情をため込まず、建設的に職場で共有し、仕組みとして改善していくことです。
Q2:体調不良でよく休む人に、どう声をかければいいですか?
A:責めるのではなく、気遣う姿勢を意識するのがポイントです。
「大丈夫?何か手伝えることがあったら言ってね」といった一言でも、相手への印象は大きく変わります。不満やイライラがあっても、まずは相手の状況を理解しようとする姿勢が、関係性の改善に役立ちます。
Q3:上司が何も対応してくれないときはどうすればいい?
A:まずは具体的な事実と要望を整理して、冷静に相談してみましょう。
単なる不満ではなく、「業務が回らない状況」「負担が偏っている現実」などを具体的に伝えることが大切です。それでも改善されない場合は、人事部門や外部相談窓口を活用する方法もあります。
Q4:そもそもなぜ頻繁に体調不良で休む人がいるのでしょうか?
A:身体的な病気だけでなく、精神的な不調が背景にあることもあります。
見た目ではわかりにくい疾患や、ストレス、家庭の事情など、さまざまな要因が隠れていることがあります。一方的に責めるのではなく、必要に応じて職場全体でのサポートを検討することが望ましいです。
なぜこの問題が起きるのか?背景と原因を整理しよう
職場で誰かが頻繁に体調不良で休む状況には、いくつかの背景や原因があります。まずはその構造を理解しておくことが、建設的な対応の第一歩になります。
以下に、主な原因を整理してみました。
体調不良による欠勤が職場で問題になる背景には、次のような要素が絡んでいます。
| 原因 | 内容 |
|---|---|
| 業務の属人化 | 一部の人にしかできない業務が集中しているため、休まれると他の人の負担が大きくなる |
| 人手不足 | もともとの人員が足りていないため、1人の欠勤が職場全体に影響する |
| コミュニケーション不足 | 状況の共有や引き継ぎがうまくできておらず、混乱が生じる |
| 柔軟な制度の未整備 | テレワークや業務分担制度が整っておらず、カバー体制が不十分 |
| 感情の蓄積 | 周囲の不満が表に出せず、ストレスとして蓄積されていく |
このように、問題の本質は個人の体調不良そのものではなく、職場の仕組みや体制にもあることが分かります。
職場全体で できる5つの対応と改善策
問題の原因が明確になったところで、次に必要なのは「どう対応するか」。ここからは、職場全体として取り組める対応策を5つの視点からご紹介します。
問題の原因が明確になったところで、次に必要なのは「どう対応するか」。まずは優先順位をつけ、影響の大きい部分から対処することが重要です。また、関係者との連携を密にし、情報共有を徹底することで、対応のズレや重複を防げます。
さらに、短期的な応急処置だけでなく、再発防止に向けた根本的な対策も同時に検討しましょう。
① 業務の見える化を進める
属人化を防ぐためには、業務内容の見える化が重要です。誰が何を担当しているのかが明確になることで、突然の欠勤にも柔軟に対応できます。
| 対策 | 実施方法 |
|---|---|
| 業務マニュアルの作成 | 日常業務の手順をドキュメント化して共有する |
| タスク管理ツールの導入 | タスク状況をチームでリアルタイムに把握できるようにする |
| 定期的な業務共有会議 | チーム内での情報共有を習慣化する |
② フォロー体制の整備
急な欠勤時に慌てないよう、誰がフォローに入るかの体制をあらかじめ決めておくと安心です。
| 対策 | 実施方法 |
|---|---|
| 役割分担の明確化 | 補助的な担当者をあらかじめ設定しておく |
| シフト制の導入 | 複数人で交代しながら対応できる体制を整える |
| 緊急時マニュアルの整備 | 欠勤時の対応手順を事前に決めておく |
③ 柔軟な働き方の導入
体調が不安定な人でも働ける環境づくりが、欠勤の予防にもつながります。
| 対策 | 実施方法 |
|---|---|
| テレワークの導入 | 通勤負担を減らし、在宅での業務を可能にする |
| フレックスタイム制度 | 体調に合わせて勤務時間を調整できるようにする |
| 短時間勤務制度 | 状況に応じた柔軟な勤務スタイルを選択肢として用意する |
④ コミュニケーションの活性化
休む人への不満がたまらないよう、オープンなコミュニケーションが重要です。
| 対策 | 実施方法 |
|---|---|
| 定期的な1on1ミーティング | 不安や不満を共有する機会を設ける |
| フィードバック文化の醸成 | 相手を責めずに気持ちを伝える方法を浸透させる |
| チームビルディング活動 | 相互理解を深める機会を意識的に作る |
⑤ メンタルヘルスへの理解と支援
体調不良の背景にはメンタルの問題が潜んでいることも多く、無視できません。
| 対策 | 実施方法 |
|---|---|
| 産業医や外部カウンセラーの活用 | 心身の状態を専門家に相談できる環境を整備する |
| ストレスチェックの定期実施 | 心の健康状態を定期的に把握する仕組みを導入する |
| 心理的安全性の確保 | 気軽に体調のことを話せる職場づくりを目指す |
前向きな気持ちを忘れずに
誰かが体調不良で休みがちになると、つい自分ばかりが損をしているように感じることもあるかもしれません。でも、その気持ちをただ我慢するだけでは、あなた自身もつらくなってしまいます。
職場全体で改善に取り組むことで、少しずつ状況は変えられます。そして、困っている人に寄り添える環境は、長い目で見れば自分自身にとっても働きやすい職場をつくることにつながるのです。
協力できる職場づくりが、すべての人を助ける
体調不良で休みがちな人がいる職場では、どうしても不満やストレスがたまりやすいものです。しかし、問題の背景を正しく理解し、職場全体で柔軟に対応していくことで、みんなが少しずつ楽に働けるようになります。
「誰かがつらいとき、自分たちにできることは何か?」そんな視点を持てる職場は、どんな困難も乗り越えられるはず。あなたの一歩が、職場全体を変える力になるかもしれません。