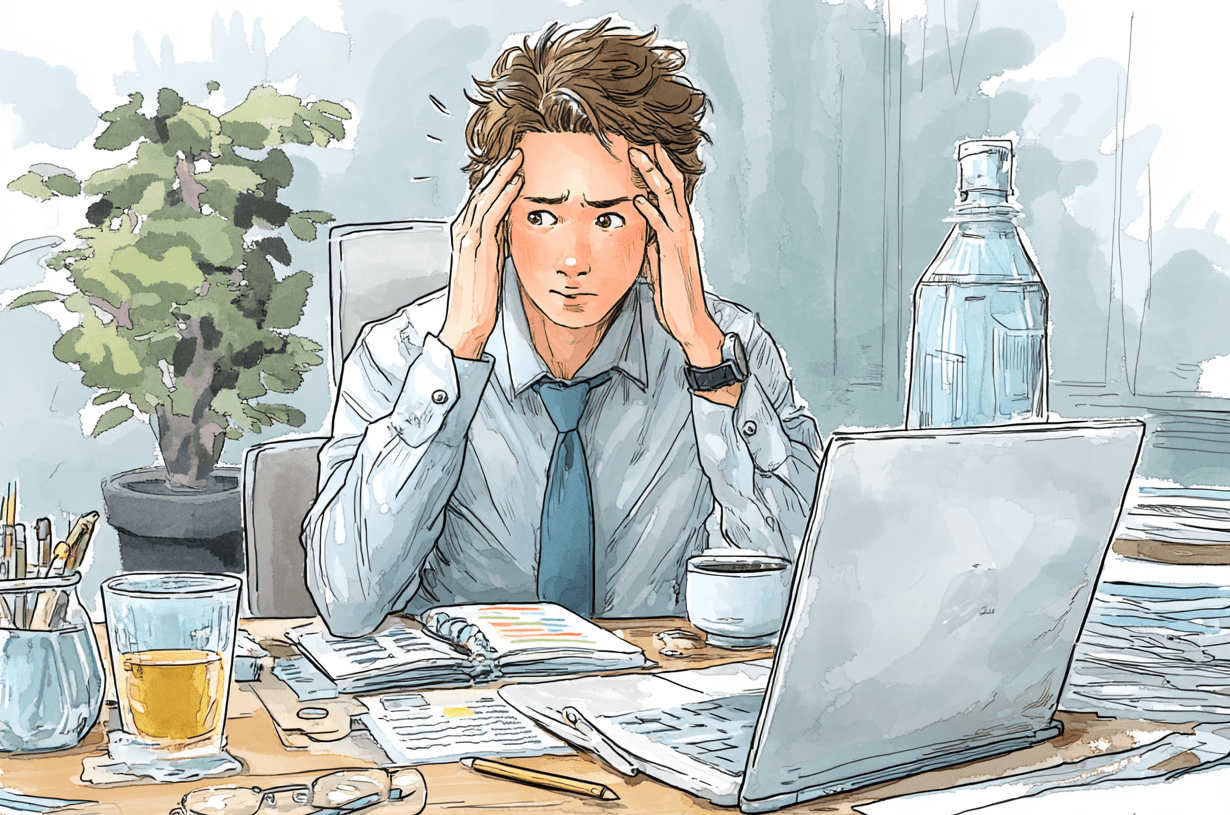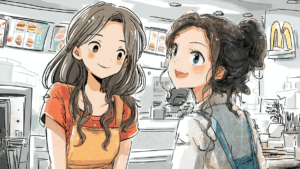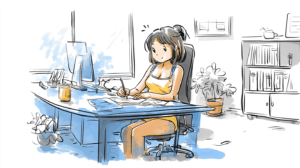つらい気持ちをわかってもらえない苦しさ
体は元気そうに見えるけれど、心がしんどくて動けない――そんな経験はありませんか?心の病気は目に見えない分、周囲に理解されにくく、「仮病じゃないの?」と言われてしまうこともあります。自分ではどうしようもない不安や倦怠感に襲われているのに、信頼している人からそんな言葉をかけられるのはとてもつらいものです。
この記事では、心の病なのに仮病と思われたときにどう対処すればいいのか、その背景や原因、そして実践的な対応策までを丁寧に解説していきます。
以下に「心の病なのに仮病と思われた」状況に関するリアルな体験談風のエピソードを5つご紹介します。それぞれ違った立場や背景を持つ人の視点で描いています。
精神的な病を「仮病」と誤解された経験者に聞く──リアルな声で綴るQ&A
Q1:仮病扱いされたとき、最初はどう感じましたか?
A(30代・会社員・男性):
一言で言えば、「信じてもらえなかった悲しさ」と「自分への怒り」が混ざったような感覚でした。
上司から「またか、サボりだろ?」と言われたときは、本当に心が折れました。心が苦しいことを説明しようとしても、途中で話すのをやめてしまいました。
Q2:実際にはどんな症状があったのですか?
A(40代・主婦・女性):
朝起きられない、家事が手につかない、意味もなく涙が出てくる…。でも見た目は普通に元気そうに見えるみたいで、「そんなに元気なら大丈夫でしょ」と言われ続けていました。
笑っている自分が、自分じゃないような気がして怖かったです。
Q3:家族や友人に分かってもらえた瞬間はありましたか?
A(20代・大学生・女性):
はい。最初は母に「甘えてる」と言われて、誰にも相談できませんでした。でもカウンセラーの方が「お母さんと一緒に来てみませんか」と言ってくれて、話し合う機会ができたんです。
時間はかかりましたが、少しずつ母も理解を示してくれるようになりました。
Q4:どのタイミングで「医療の助けが必要だ」と感じましたか?
A(30代・IT勤務・男性):
朝、何もできずにベッドの中で動けない自分に気づいたときです。
それでも「自分が怠けてるだけ」と思い込んでいたんですが、ネットで自分と同じような人の体験談を読んで、初めて「病気かもしれない」と思えました。そこからは勇気を出して心療内科へ行きました。
Q5:今、同じように悩んでいる人に伝えたいことはありますか?
A(10代・高校生・男性):
無理に分かってもらおうとしなくていいと思います。本当に苦しいときは、無理に説明しようとすると逆に心がすり減るから。
誰か1人でも味方になってくれる人がいれば、そこから道が見えてくる。僕は担任の先生がその1人でした。自分を責めないでください。
目に見えない「心の病」は、まだまだ誤解や偏見が残っています。でも、体験者の声には、同じように悩んでいる人を救う力があります。
誰かに否定されても、あなたの感じている苦しみは本物です。このインタビューが、少しでも心の支えになれば幸いです。
「仮病」と誤解された5つの体験談
1. 会社の上司に「サボりたいだけだろ」と言われた(30代・男性)
長時間労働とプレッシャーでうつ状態になり、心療内科に通っていたのですが、診断書を提出しても上司には「また仮病か。結局サボりたいだけなんだろ」と一蹴されました。
心が折れそうになりましたが、労働組合に相談し、配置転換と休職が認められました。今は療養しながら少しずつ回復しています。
ある日、朝になるとベッドから起き上がれなくなり、胸の圧迫感と動悸に襲われるようになりました。食欲もなく、夜も眠れず、ただ焦燥感だけが増していく日々。
心療内科を受診した結果、「うつ病」と診断され、しばらく休職することに。しかし、直属の上司に診断書を提出した際、鼻で笑うようにこう言われたのです。
「またかよ。サボりたいだけじゃないの?他のやつはちゃんと出てきてるんだよ」
その言葉に、心がズタズタに引き裂かれたような気持ちになりました。これまで頑張ってきた日々が全否定されたようで、自分の存在価値すら分からなくなったそうです。
それでも、自分を守るために人事部と労働組合に相談。第三者を介して状況を説明し、職場とのやりとりも代行してもらいました。結果的に正式な休職が認められ、加療と回復の時間を得ることができました。
本人は「職場に戻る勇気は正直ないけど、自分の命を守れたのはあの時行動したから」と語ります。あのとき声を上げなかったら、もっと取り返しのつかないことになっていたかもしれません、と。
2. 家族に「甘えてるだけ」と否定された(20代・女性)
大学で人間関係に悩み、摂食障害とうつを発症。でも実家に帰ると、母親から「そんなのは甘え」「心が弱いからだ」と言われ、とても孤独でした。
地方から都市部の大学に進学し、一人暮らしを始めてから、少しずつ心が沈んでいくのを感じていました。きっかけは友人関係のトラブルと、期待に応えようとするプレッシャー。ある日、食欲がなくなり、体重が急激に減少。眠れず、授業にも出られなくなりました。
気づけば、自室のベッドから動けなくなっていました。
不安でいっぱいになり、久しぶりに実家に電話をかけ、「どうしても大学に行けない。苦しい」と打ち明けたところ、母親から返ってきたのは意外な言葉でした。
「そんなのは甘えでしょ。みんな嫌なことあっても頑張ってるのよ?」
頭が真っ白になりました。心から助けを求めた相手に、否定された――それだけで、さらに深く孤独を感じました。「私はだめな人間なんだ」と自分を責め続け、自傷行為に及びそうになったこともあります。
そんなとき、大学の保健センターでたまたま出会った職員が親身に話を聞いてくれ、心療内科への受診を勧めてくれました。診断は「適応障害と軽度のうつ」。その言葉を聞いたとき、「やっぱり私は甘えてたんじゃなかった」と、涙が止まりませんでした。
現在はカウンセリングを受けながら、通信制の講義に切り替えて少しずつ生活を整えています。母との関係も少しずつ修復し、「あのときの私は、あなたのSOSに気づけなかった」と言ってくれるようになりました。
3. 元気そうに見える自分に苦しんだ(40代・女性)
40代前半の女性、二児の母でパート勤務。
心は不安定で涙が止まらないのに、外に出ると笑顔を作ってしまう自分がいました。すると周囲からは「そんなに元気なら仕事できるでしょ?」と…自分でも「本当に病気なの?」と疑うことも。
今は無理に笑うのをやめて、信頼できる人にだけ本音を話すようにしています。
家事も育児もきちんとこなし、周囲からは「しっかりしていて明るい人」と見られていました。でも実際は、心が空っぽのように感じていて、家族といてもどこか孤独。夜になると涙が出て眠れない日々が続いていました。
ある日、職場でささいなことで責められた瞬間、堪えていたものが溢れ出し、トイレで声を殺して泣いたのを今でも覚えているそうです。それでも家に帰れば笑顔で家族を迎え、子どもの宿題を見たり夕飯を作ったり…。周囲には「全然元気そうに見えるよね」と言われ続けました。
自分でも「これって本当に病気なの?」「気の持ちようじゃないの?」と疑ってしまい、誰にも助けを求められませんでした。
あるとき、たまたまネットで「微笑みうつ」という言葉を見つけ、自分とぴったり重なる症状に驚きました。勇気を出して心療内科を受診すると、「うつ状態」と診断されました。
「あなたのように“元気そうに見せてしまう人”ほど、周囲から見過ごされやすいんですよ」と医師に言われて、ようやく自分の苦しさが本物だと実感できたそうです。
今では家族にも打ち明け、家事を手伝ってもらいながら、無理なく仕事を続けています。「笑顔をやめることで、自分を守れるようになった」と話してくれました。
4. SNSで仮病扱いされた(10代・男性)
不登校になった理由が心の不調だったのに、SNSで「〇〇って仮病で学校サボってるらしいよ」と言われてショックでした。
でも、先生と親が本気で守ってくれて、今はフリースクールで学び直しています。誰か1人でも味方がいれば救われるんだと実感しました。
中学までは明るくて活発、クラスでも中心的な存在でした。しかし、高校に進学してから環境が合わず、友人関係のストレスや成績のプレッシャーで、少しずつ教室に行くのが怖くなっていきました。朝になると吐き気や頭痛に悩まされ、ベッドから起き上がれなくなりました。
勇気を出して「学校に行けない」と親に打ち明け、心療内科に通い始めたころ。クラスのグループLINEで、ある噂が流れ始めたのです。
「〇〇(彼の名前)、仮病でサボってるらしいよ」
「ただのサボり魔じゃんw」
SNS上で広がる悪意のない“冗談”のような言葉が、彼の心に深く突き刺さりました。本当は誰よりも教室に戻りたかった。でも、どこにも味方がいないような気がして、スマホの電源すら入れられなくなりました。
そんな彼を支えてくれたのが、担任の先生と母親でした。先生は定期的に電話をくれ、「無理しなくていい。でも、君の居場所はここにある」と言い続けてくれました。母親も、何も言わずに隣にいてくれる存在でした。
その後、地元のフリースクールに通うようになり、少しずつ日常を取り戻していきました。SNSでの傷は今でも完全には消えませんが、「誰か1人でも本気で信じてくれる人がいれば、前に進める」と語ります。
5. 自分でも自覚が遅れた(30代・男性)
ずっと無気力で、毎朝起きるのがつらい。でも「ただ怠けてるだけ」と思い込んでいて、会社に行けない日も自分を責めていました。
限界がきて心療内科を受診し、うつ病と診断されました。自分自身が「仮病じゃない」と認めることも、すごく大事なんだと学びました。
30代後半の男性、IT企業で働くサラリーマン。入社以来、長時間労働と納期のプレッシャーに追われ続ける日々でした。周囲は忙しくても笑顔で乗り切っているように見え、「自分だけ弱音を吐いてはいけない」と、無理を重ねて働き続けました。
ある日、ふと朝起きられなくなり、スーツに着替える気力も出ない。たまったメールを見ても手が止まる。「ただサボりたいだけなのか?」と自分を責めながら、何度もベッドに戻るようになりました。
最初は「自分の怠け癖が出ただけ」と思い、家族にも「ちょっと疲れてるだけ」とごまかしていました。でも、その状態が何週間も続き、好きだった趣味にも手がつかず、笑うことすらできなくなった頃、「これはおかしい」とようやく気づいたといいます。
心療内科での診断は「中等度のうつ病」。医師の「ここまでよく耐えましたね」という言葉に、涙が止まらなかったそうです。自分で自分の不調を否定していたことが、さらに苦しみを深めていたのだと気づかされました。
今では数ヶ月の休職を経て、時短勤務とカウンセリングを並行しながら少しずつ社会復帰しています。周囲に心の不調をオープンにするのは勇気が必要でしたが、「もっと早く受診していればよかった」と今では語ります。
「『怠けてるだけ』という言葉は、自分の命を削る刃になる。あの時、医師に出会えなかったら、今の自分はいなかったかもしれない」
これらの体験談は、読者に「自分だけじゃない」と思ってもらえる効果があります。記事への挿入や別記事の素材としても活用できますので、ご希望があれば編集・追加も可能です。
なぜ心の病は「仮病」と誤解されるのか?
心の病が仮病と誤解されるのには、いくつかの理由があります。ここでは、主な背景をわかりやすくまとめた表をご紹介します。
精神的な不調が理解されにくい理由を知ることで、自分を責めずにすむ気持ちの余裕が生まれるかもしれません。
| 誤解の原因 | 説明 |
|---|---|
| 見た目に異常がない | 心の病は外見では分かりにくく、「元気そう」に見えてしまうことがある |
| 社会的な無理解 | 精神疾患に対する知識や理解が不足しており、誤解が生じやすい |
| 根性論や精神論の文化 | 「気合で乗り切れ」という風潮が残っているため、心の弱さを許容しづらい |
| 自分の説明不足 | 状況をうまく伝えられず、相手が誤解してしまうこともある |
| 他者の経験不足 | 心の病に関わった経験がない人は、想像しづらく共感しにくい |
対応策と心のケア方法
では、実際に「仮病でしょ?」と言われたとき、どうすればいいのでしょうか?以下では、実践的な対処法を5つの視点から紹介していきます。
① 無理に説明しすぎない
無理に分かってもらおうとすると、かえって心が疲れてしまうことがあります。まずは自分を守ることを優先しましょう。
| ポイント | 説明 |
|---|---|
| 自己防衛を意識する | 無理解な人に無理に説明するのは逆効果。自分のエネルギーを消耗するだけになることもある |
| 信頼できる人にだけ話す | 全員に理解を求めず、信頼できる人にだけ状況を共有するのが効果的 |
② 医師の診断書を活用する
心の不調は客観的な証明が難しいですが、診断書があることで状況を伝えやすくなります。
| ポイント | 説明 |
|---|---|
| 医療の専門性を借りる | 医師の言葉は説得力があり、周囲の理解を得やすい |
| 診断書の提出を検討 | 職場や学校などでは、診断書を提出することで誤解を和らげる効果がある |
③ 知識不足を責めない
誤解する人を敵視してしまうと、余計に人間関係が悪化します。相手の無知を責めるより、自分の心を保つことを意識しましょう。
| ポイント | 説明 |
|---|---|
| 無理解=悪意ではない | 知識がないだけで、悪意があるとは限らない |
| 説明が難しければ専門書や資料を見せる | 自分の言葉で伝えるのが難しい場合は、第三者の情報を活用する方法もある |
④ 無理に元気なふりをしない
周囲に気を遣って無理をしすぎると、心の状態がさらに悪化します。
| ポイント | 説明 |
|---|---|
| 無理な演技は逆効果 | 「元気そうに見せる」ことが、誤解を深める原因にもなる |
| 正直な状態を保つ | つらいときは「つらい」と正直に受け止めることが回復への第一歩 |
⑤ 専門家に相談する
一人で抱え込まず、心療内科やカウンセラーに相談することで、適切なサポートを受けることができます。
| ポイント | 説明 |
|---|---|
| 第三者の意見を得る | 専門家の視点でアドバイスをもらうことで冷静になれる |
| カウンセリングで気持ちの整理 | 誰かに話すことで心が軽くなることも多い |
気持ちの持ち方:あなたの感覚は間違っていない
「仮病」と言われると、つい「自分が弱いのかな」と思ってしまいがちです。でも、それは間違いです。あなたが感じている苦しさは本物で、誰かと比べる必要はありません。
周囲に理解されないからといって、自分を否定しないでください。心が疲れているときこそ、自分を一番大切にするべきです。
心の病は、外からは見えづらく誤解されやすいものです。
「仮病じゃないの?」という言葉に傷ついたとしても、あなたの感じている苦しみは事実です。まずは自分を守ること、そして信頼できる人や専門家に頼ることが大切です。
無理せず、少しずつ自分のペースで回復していきましょう。あなたは一人じゃありません。